|
旧日光街道巡り 1 |
|
「ねりま区報」のミニガイドに掲載された、NPO法人スポーツクラブホワイエ上石神井主催「旧日光街道・千住宿を歩く」
に参加しました。 丁度、「日光街道」について調べていたところでしたので、タイムリーな企画にめぐり合えたと期待でワクワクです。 江戸時代の五街道のうち日光街道の、日本橋を発って最初に到着する宿場町が「千住」です。 今回は、南千住駅〜千住大橋〜北千住〜荒川土手までの約6Kmの区間を、ほぼ旧日光街道に沿って歩くという企画です。 ルートマップは、「地図Z 坂道散歩(日光街道日本橋→千住宿)」が参考になるのでリンクさせていただきました。 9時にJR常磐線南千住駅に集合したのは、案内人の峰岸さん・川崎さんのほか9名でした。 高架沿いに進むと、旧日光街道の「コツ (骨) 通り」にでます。 この辺は昔「小塚原刑所」があり受刑者の亡骸を埋めるのに深く掘らなかった為、荒されて骨が出易かったということです。   南千住駅北口 コツ通り コツ通りの左正面に、葵紋を掲げたコンクリート造りの白い建物が「豊国山回向院」別称 小塚原回向院 です。 両国回向院の別院で、近くにあった小塚原刑場で処刑された人々を供養するため創建された寺です。 入り口左手に、戦後最初の児童営利誘拐殺人事件をともらう「吉展地蔵尊像」がありました。 墓地に柵で覆われた一角があり、荒川区有形文化財の「橋本佐内・吉田松陰・頼三樹三郎」の国事犯とか、「腕の吉三郎・ 鼠小僧次郎吉・高橋お伝・片岡直二郎」など有名悪人の墓がありました。 橋本佐内の墓だけが立派なお堂に入っていま した。  回向院    駐車場のような入り口 入口右手の壁に観臓記念碑 同 拡大画像    右側柵内に有名人の墓 左) 高橋お伝の墓 左) 鼠小僧次郎吉の墓 右) 野出の喜三郎の墓 右) 片岡直次郎の墓    吉田松陰の墓 橋本佐内の墓 (堂宇内) 地蔵菩薩像   地蔵菩薩像 青銅の吉展地蔵尊 回向院前の通りと交差するJR鉄道高架のガード下をくぐると、「史蹟小塚原刑場跡」と「豊国山延命寺」のプレートが目 に付きました。 このあたりは小塚原といい江戸時代に刑場のあった場所で、刑死者の菩提を弔うために作られたものです。 「小塚原刑場跡」は、荒川区有形文化財に指定されています。 眼前には、高さ3 .6mの大きな「延命寺首切地蔵」が見据えています。 この首切地蔵、27個の花崗岩を組み合わせて作 られたのだそうで、よくみると一つ一つのパーツを合わせてあるのが分かります。  史跡 小塚原刑場跡銘板    小塚原刑場跡 馬頭観世音の石碑 百度石 題目塔と首切り地蔵像 大正五年(1916) 造立    地蔵菩薩像 首切り地蔵像 つなぎ目 寛保元年(1741) 造立 回向院まで戻ります。 旧日光街道は、コツ通りを直進し素盞雄神社で国道4号線 (日光街道) と合流します。 今回は、コツ通りを200mほどの交差点で左折 300m進み、国道4号線沿いの円通寺に向かいます。   コツ通り (旧日光街道) 国道4号線 (日光街道) 日光街道を左に120m進むと、鉄筋コンクリート造りで本堂の上に高さ12メートルもある金色の聖観音像が安置された 異様な塔を有する「補陀山円通寺」に着きました。 上野戦争最激戦となった「寛永寺の黒門」には、無数の弾痕が残されていました。 彰義隊士の遺骸266体を手厚く合葬した 荒川区史跡「死節の墓」も、柵に覆われて安置されています。 百観音で有名と聞いていましたが、「西国・坂東・秩父/百くかんおんの石碑」だけがありました。    寺院門碑と本殿 宋風獅子型狛犬 寛永寺の黒門    死節の墓 石仏群 如意輪観音像    六地蔵像 馬頭観音像と地蔵菩薩像 八幡太郎義家が築いた首塚    首塚に建つ七層の石塔 玄関脇に金剛力士像 百くかんおんの石碑 円通寺を日光街道に沿って東へ400m進むと、日光参詣の道筋となっていた「下谷道」の案内標識がありました。 日光街道から素盞雄神社までは、下谷道の一部を歩くことになります。   途中に千住間道の道標 下谷道 下谷道を180m程歩くと、八俣大蛇を退治した伝説の「素盞雄 (スサノオ) 神社」の鳥居に出ました。  境内Map 素盞雄大神の社殿が西向きに、飛鳥大神の社殿が南向きに造営されていました。 境内の隅に、「地蔵堂」と呼ばれる荒川区有形民族文化財に指定された江戸時代の「庚申塔三基・宝篋印塔一基」などから なる石塔群が配置されていました。    明神型一之鳥居 明神型二之鳥居 鳥居前 和風獅子型狛犬   本殿 本殿前 宋風獅子型狛犬    地蔵堂の一角 同 左から 宝篋印塔 同 庚申塔前 和風獅子型狛犬    同 庚申塔 拡大画像 同 聖観音菩薩像 同 青面金剛塔 延宝六年(1678) 造立 日光街道に面して、素盞雄神社・飛鳥神社両社の額を掲げた大鳥居がそびえていました。 こちら側が飛鳥神社の領域なのでしょうか。    素盞雄神社 神社名碑 日光街道側 明神型大鳥居 飛鳥神社 拝殿 本殿の右側に、荒川区指定史跡の「南千住富士塚」がありました。 小塚原の小塚に溶岩を積み増しして、高さ4m程度の富士塚になっています。 周りは柵で囲まれており,鳥居の前には太い竹棒が横に置いてあり,登山禁止になっています。 「富士浅間社」となっておりますが、その中腹の祠の中に「瑞光荊石」が祀られていました。    浅間神社 明神型一之鳥居 境内 神明型二之鳥居 覆屋に瑞光荊石    登山道入口に浅間神社の石碑 富士講の石碑 頂上を臨む   頂上 小社 同 拡大画像 素盞雄神社の大鳥居から230mで、隅田川筋では最も古い「千住大橋」です。 橋の袂に珍しく、「八紘一宇」の石碑がありました。 千住大橋を境に、荒川区から足立区に入ります。 全長91.5mの千住大橋を渡りきった袂の大橋公園の案内板に、「松尾芭蕉はこの辺りから陸路奥の細道へと旅立った」と ありましたので、階段を下って川べりまで下りてみました。   千住大橋 このあたりに八紘一宇の石碑   橋の下を遊覧船が 芭蕉が旅立った辺り 公園の角を左折し100m入った突き当たりの緑の多い所が「橋戸稲荷神社」です。 「本殿」は、区内唯一の土蔵づくり本殿として、昭和57年に足立区有形文化財(建造物)に登録されています。 本殿扉の左右には、伊豆長八による漆喰鏝絵「親子狐」が置かれていました。 色褪せしていない瑞々しい漆喰装飾に、暫し見惚れてしまいました。 鳥居は石や木の物ではなく、珍しく銅版で覆われていました。   銅版の神明型鳥居 本殿   狐の鏝絵 躍動的なお稲荷さま 文久三年(1863) 作成 橋戸稲荷神社から200m、国道4号の日光街道を左に分けて、右へ行く道が旧日光街道になります。  左 日光街道、右 旧日光街道 千住大橋から始まり荒川方水路にかかる千住新橋付近までが、「千住宿」であったようです。 千住が日光街道の初宿ということです。 たかだか9Km程度の道程でと思いましたが、案内人の「帰りの方の最後の宿でもあった」という説明に納得しました。 旧日光街道の道幅は、今でも五間 (9m) の寸法のまま受け継がれているとのことです。 ここからの300m近くの通りは、元やっちゃ場といい、多数の青果問屋が道の両側に軒を並べていました。 少し進むと左の家の壁に、「此処は/元やっちゃ場/南詰」の札が掲げられていました。 更に進むと、「旧日光道中/是より西へ大師道」の石碑がありました。 墨堤通りに出ると千住仲町商店街のアーケードが見えてきますが、ここがやっちゃ場の北詰になります。    やっちゃ場入り口に千住宿の道標 やっちゃ場南詰めの案内板 旧日光街道の道標  やっちゃ場の北端 千住仲町商店街入り口に、千寿七福神の寿老人を祀る「稲荷山勝林院源長寺」がありました。 境内の石造物に興味を示していましたら、案内人が「落語名人三遊亭円朝寄進の石灯篭」を教えてくれました。    寺院名碑と山門 延命子育地蔵のお堂 同 拡大画像    旧跡延命子育地蔵堂の石碑 工事中の本殿 寿老人像    十三層の石塔 境内の稲荷神社 二基の馬頭観世音の石碑    左) 阿弥陀如来坐像の庚申塔 青面金剛像の庚申塔 地蔵菩薩像 寛文四年(1664) 造立 享保十年(1725) 造立 右) 青面金剛像の庚申塔 元禄九年(1696) 造立    地蔵菩薩像 多宝塔 円朝寄進の織部型灯篭 320m程の仲町商店街を進んだ交差点の左側に、「千住高札場跡の石碑」がありました。 信号を渡った千住一丁目から五丁目までの南北1km余りの一帯は、千住宿として最も早くから機能したことから宿の行政 や宿泊地の中心として発展していたようです。 一丁目の南詰近くに「千住宿/問屋場貫目改所跡」の標柱がありました。    千住高札場跡石碑 千住一丁目の旧日光街道 千住宿/問屋場貫目改所跡の標柱 標柱を左に入った突き当たりに、江戸城北方の鎮護寺として寺紋に葵の紋を許された寺院「稲荷山慈眼寺」がありました。   参道 立葵紋が付いた山門   地蔵堂 同 地蔵菩薩像 拡大画像    日限地蔵尊の線彫り像 地蔵像の庚申塔 聖観音像 左) 寛文七年(1667) 造立 元禄六年(1693) 造立 右) 万治三年(1660) 造立    宝筐印塔 六地蔵像 不動明王 など 宝暦四年(1754) 造立   本殿 豊川枳尼眞天のお社 慈眼寺の右隣りが、千寿七福神の福禄寿を祀る「白幡山不動院薬師寺」です。    寺院門碑 左) 角柱型文字庚申塔 豊川枳尼眞天のお社 安永六年(1777) 造立 中) 青面金剛像の庚申塔 元禄十五年(1702) 造立 右) 庚申の石碑 文化十一年(1814) 造立    福禄寿像 本殿 不動明王像 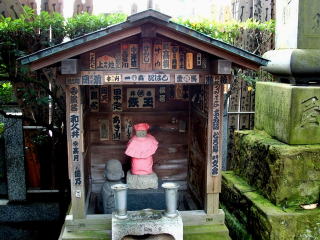  地蔵堂 同 拡大画像 不動院を出て直ぐの角を左折し200m進んだ突当りが、千寿七福神の毘沙門天を祀る「三宮神山大鷲院勝専寺」通称 赤門寺 です。   寺院門碑 鐘楼    観音堂 毘沙門天像 馬頭観世音の石碑    六地蔵像 閻魔堂 同 赤顔赤服の閻魔大王   明治のモダンな本堂 赤門 寺の向いにある住宅の軒先に、「不動明王像」と「四面仏の手水鉢」が置かれていました。 賑やかな本町センター商店街 (旧日光街道) を突っ切って、金蔵寺に向かいます。    不動明王像 四方仏の手水鉢 本町センター街 勝専寺から200m北千住駅方向に進むと、「氷川山地蔵院金蔵寺」別称 投込寺 に出ます。    寺院門碑 阿弥陀如来立像の庚申塔 六地蔵像  本殿 再び本町センター商店街に戻り、暫らく進むと北千住駅前通りの交差点に出ます。 金蔵寺から230m進みました。 右手に東武伊勢崎線北千住駅を見ながら道路を横断して、宿場町通りサンロード商店街を歩きます。 100円ショップの脇に「千住宿本陣跡の標柱」を見つけました。 ここが千住宿の中心とのこと。 大名行列を避けるための路地が、現在でも繁華街の中に沢山残っているのが印象的でした。    右手正面が北千住駅 宿場町通り商店街 千住宿本陣跡の標柱  このような路地が多い 道の右側に、現在も住居として使用されている重厚な商家造りの「横山家」が千住宿の名残を留めています。 千住四丁目のはずれに、「北へ 旧日光道中/東へ 旧水戸佐倉道」の道標がありました。 千住宿を通る旧日光街道は、ここで終りのようです。 やっちゃ場入り口から、約1600mの道程でした。   横山家住宅 旧日光街道の道標 そのまま真っ直ぐ、荒川に向かい歩を進めました。 100m程先の角に、「北西に 旧日光道中/北へ 下妻道」の道標がありました。 道標を真っ直ぐ下妻道を進みます。 直ぐ向かい側に、明和年間 (1764〜) に開業した歴史ある接骨医院「名倉医院の長屋門」が見えました。   旧日光街道の道標 名倉医院の長屋門 目の前は、「荒川」の土手です。 土手にあがると荒川と千住新橋の広い景色が目の前に展開し、まさに「3年B組金八先生」の世界です。 この川は、昭和5年に荒川放水路として人工的に造られたもので、江戸時代には存在しなく、旧日光街道は千住新橋の袂 から対岸まで西へ斜めに走っていたようです。 今回の企画「旧日光街道・千住宿を歩く」は、ここで解散になります。 丁度12時です。 青空と清々しい空気をご馳走に昼食を済ませ、この先の寺院巡りに思いを馳せました。  荒川 先ほどの「北西に 旧日光道中/北へ 下妻道」の道標まで戻り、日光街道方向に進むと「西林山長福寺安養院」の山門に 出ました。 荒川土手から240m歩いたことになります。 山門は閉じられていましたが、通用門から入ると、山門の右手にお顔が剥落した「カンカン地蔵尊」がありました。   山門 山門の前に三基の石仏    同 剣人六手青面金剛像の庚申塔 同 地蔵像の庚申塔 同 合掌六手青面金剛像の庚申塔 貞享三年(1686) 造立 寛文十年(1670) 造立 元禄十五年(1702) 造立    寺院名碑 楽堂 本殿   六地蔵尊 同 拡大画像   本殿前 大師堂 同 堂内に石祠    左) カンカン地蔵像 墓地入り口の宝筐印塔 本殿前の宝筐印塔 元禄十二年(1699) 造立 なかよし地蔵像 中) 寛文四年(1664) 造立 右) 寛文十年(1670) 造立 安養院を「北へ 旧日光道中/東へ 旧水戸佐倉道」の道標まで戻り、更に水戸佐倉道沿いに270mいくと「千住氷川神社」 に出ます。 拝殿の左側には、境内社「高正天満宮」がありました。   明神型の鳥居 拝殿  拝殿前の和風獅子型狛犬   高正天満宮の神明型鳥居 同 拝殿   同 石段前 宋風獅子型狛犬 同 拝殿前 和風獅子型狛犬   三管塚 塞大神の石碑 氷川神社を出た直ぐ隣に、「目やみ地蔵尊」が祀られています。 長円寺の壁に挟まれた形で、1畳程の小さいスペースに、地蔵堂・のぼり旗・絵馬の奉納場所・輪廻車などが窮屈に配置さ れていました。   地蔵堂 目やみ地蔵尊像 地蔵堂に隣接して、千寿七福神の布袋尊を祀る「月松山照光院長円寺」があります。 山門の左側には、氷川神社の本地佛と伝えられる石造の「魚籃観音像を祀る小堂」がありました。 山門の右側には、板石に本尊が線彫りされた「四国八十八ヶ所巡り毛彫り石碣」が配置されていました。    山門 魚籃観音のお堂 同 魚籃観音像  本殿   境内右手に石仏群 六地蔵像   左) 一字金輪佛頂尊座像 青面金剛像の庚申塔 寛文四年(1664) 造立 貞享三年(1686) 造立 右) 来迎弥陀立像    八十八ヶ所霊場の石碑 線彫り仏の霊場 同 不動明王の線彫り    霊場内に布袋尊像 霊場内の太子堂 同 弘法太子 拡大画像   場内に魚籃観音像 宝筐印塔 享保十七年(1732) 造立 長円寺から西へ、宿場町通り商店街を縦断し340mのところに、千寿七福神の大黒天を祀る「本氷川神社」がありました。 藤棚に覆われた二基の鳥居の奥にある、重厚な旧社殿内に大黒天が祀られています。    明神型一之鳥居 明神型二之鳥居 千寿七福神の碑   旧社殿 同 社殿内 大黒天像   三精稲荷の神明型鳥居 同 お社   神社の一番奥に構える社殿 社殿前に宋風獅子型狛犬 再び、千住一番の繁華街 千住三丁目から五丁目まで続く宿場町通り商店街(サンロード商店街)をゆっくりと満喫し、 440m先の JR常磐線北千住駅に着いたのは、13時10分でした。   商店街路地奥に銭湯 北千住駅 今回は、NPO法人 スポーツクラブホワイエ上石神井主催の企画に乗った「旧日光街道・千住宿巡り」でしたが、参加者が 少なかったこともあり運営がスムースに行き過ぎて、当初予定よりも3時間以上も早く解散になりました。 それではと、最寄のJR常磐線北千住駅までの幾つかの神社・寺院を巡ってみることにしました。 お陰で、北千住駅付近に点在する千寿七福神のうち「布袋尊の長円寺」「大黒天の本氷川神社」「毘沙門天の勝専寺」 「福禄寿の不動院」「寿老人の源長寺」の5社を巡ることが出来ました。 先日、川越の七福神寺を巡っているだけに楽しい気分になりました。 日本橋から千住までの日光街道 (9Km) も巡らなくてはと心に誓いました。 |