|
日光街道巡り − 千寿七福神巡り |
|
2006年10月に巡った旧日光街道巡り千寿七福神の続きです。 前回、「布袋尊の長円寺」「大黒天の本氷川神社」「毘沙門天の勝専寺」「福禄寿の不動院」「寿老人の源長寺」の 5社を巡りましたが、今回は残りの「恵比寿天の千住神社」「弁財天の仲町氷川神社」を巡ります。 当日は酷暑という事もあり、無理をせずに2箇所を中心に2Km余りの行程を組みました。 9時50分に京成本線千住大橋駅に降りたちました。  千住大橋駅北口 駅構内を出て直ぐに、交通量のの激しい日光街道(国道4号線)を渡ります。 そのまま東へ少し進み、旧日光街道に出ます。 前回歩んだ旧日光街道を北へと進みます。 千住中町交差点で源長寺寺院門を左に見て右折し、墨堤通りを東へと進みます。   墨堤通り 源長寺寺院門 千住大橋駅から600mで、千寿七福神 弁財天を祀る「仲町氷川神社」に着きました。   神明型鳥居と神社名碑 拝殿   拝殿前の常夜燈 拝殿前の和風獅子型狛犬 文政二年(1819) 造立    手水舎 同 水盤 石灯篭 寛政十一年(1799) 造立 拝殿の左側に、境内社の一つ学問の神様として親しまれている「関屋天満宮」があります。 鳥居の横の「関屋天満宮の石碑」は、足立区有形民俗文化財になっています。    神明型鳥居 関屋天満宮の石碑 水盤 文化四年(1807) 造立 天明五年(1785) 造立  社殿 拝殿の右側に、境内社 千寿七福神 弁財天を祀る「江島神社」があります。 鳥居を潜った弁天池の中央に、足立区有形民俗文化財で東京で唯一といわれる 台座に三猿が彫られている「弁天像供養 庚申塔」が祀られています。    明神型鳥居 弁天池の中央に弁才天像 同 弁天像供養庚申塔 元禄二年(1689) 造立 その隣には、境内社「三峯神社と稲荷神社 (合祀)」があります。   明神型鳥居 社殿 旧日光街道に戻り、千住仲町商店街を北に進みます。 千住警察署前通りと交差したところで、左折し千住警察署前通りを西へと進みます。 この角には「千住高札場跡の石碑」が建っています。    千住仲町商店街 千住高札場跡の石碑 千住警察署前通り 仲町氷川神社から550mで、通りに面して「千龍山妙智院慈眼寺」の寺院門があります。 2006年10月に巡拝しましたが、この時は東側の山門から入りました。 今回は、南側寺院門から参拝させて頂きます。 本堂の左右には、「興教大師像」と「弘法大師像」が安置されています。 境内の右側には、江戸消防組で南北千住消防組の犠牲者の供養碑があります。   寺院門 本殿   興教大師像 弘法大師像   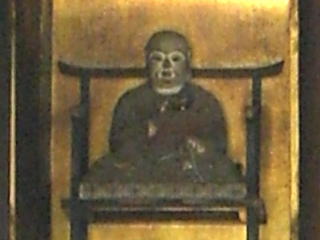 南北千住消防組供養塔 薬師堂 同 薬師如来像 千住警察署前通りと日光街道 (国道4号線) が交差する千住警察署入口交差点を渡り、北西の道を進みます。   千住警察署入口交差点付近 日光街道 (国道4号線) 慈眼寺から200mで、「千邑山常護寺」に着きました。 本堂庫裏等を一体とした、鉄筋コンクリート3階建てのこじんまりした寺院です。    寺院門 本堂 石灯篭 常護寺から100mあまりで、千住の鎮守としてこの町で最も格式の高く 千寿七福神の恵比寿天を祀る「千住神社」に出 ます。 神社名碑の右横に、「史跡八幡太郎源義家陣営の地の石碑」があります。 参道の両脇には朱のぼんぼり灯篭が並び、途中緋毛氈を引いた縁台があり風情たっぷりでした。    明神型一之鳥居と神社名碑 参道 神楽殿    手水舎 神明型二之鳥居 鳥居横 常夜燈 文政十三年(1830) 造立   参道 参道途中の常夜燈   参道途中 修復中のお稲荷さま 昭和三年(1928) 造立   和風獅子型狛犬 拝殿 文政十三年(1830) 造立 境内社の「浅間神社」の鳥居の先は、大正12年建立の高さ約5m「千住宮元富士」になっています。 この日は残念ながら施錠されており立ち入り禁止。 富士山開きの7月1日にだけ登拝できるようです。 鉄門の前の御賽銭箱の横に、一合目石がありました。 五合目辺りには、「小御嶽の石碑」もきちんと祀られていまし た。 七合目辺りには、「烏帽子岩の石碑」も見えました。 頂上には「奥宮」も祀られており、塚の右側ふもとには「御胎内」もありました。    浅間神社 神明型鳥居 一合目石 二合目石    三合目辺りの石碑 三合目石・四合目石と一心講碑 四合目辺りの石碑    五合目辺りの石碑 五合目石と小御嶽神社の石碑 六合目石・七合目石    八合目石 九合目石 頂上標柱    頂上 石祠 御胎内 富士塚の全景 境内には、このほか千住七福神の恵比寿神をはじめ多くの末社摂社が祀られています。 境内社「延命稲荷社」。 新旧のお狐様が控えています。   神明型鳥居 境内    古いお狐様 新しいお狐様 社殿 境内社「稲荷社」。 「廻転恵比寿」は、全国の七福神のなかで唯一の回る恵比寿石像です。 この恵比寿様に願掛けの方法とは、「恵比寿様を男性は左に三回、女性は右に三回廻し祈念した後、白いハンカチにて 恵比寿様の体の各祈願部位を三回なでます」。 早速、持参のハンカチで願をかけてみました。   参道 水盤    廻転恵比寿 同 簡単に廻りました 社殿 境内社「三峯神社・恵比寿神社・八幡神社」。 ここには、珍しく「和犬の狛犬」(狼には見えない) が控えていました。    明神型鳥居 和犬の狛犬 社殿 弘化二年(1845) 造立 境内社「経王稲荷神社」。 新旧三代のお狐様が控えています。   神明型鳥居 参道  宋風獅子型狛犬   子背負いのお狐様 新しいお狐様   古いお狐様 社殿 境内には「江戸大神輿 (都内でも数少ない現存する江戸時代の大神輿)倉」があり、一宮神輿・二宮神輿が披露されてい ました。 また、「八紘一宇の碑」が傾いて建っていたのが印象的でした。    神輿倉 八紘一宇の石碑 石灯籠 明冶二年(1869) 造立 千住神社から450m 千住大橋駅へ向かう途中、i日光街道沿いに ヤッチャバの鎮守「河原町稲荷神社」の大鳥居がみえ ました。 千住七福神は2008年から寺院の4箇所が神社に変更になり、「新千住七福神」になったそうです。 ここ河原町稲荷神社は、新千寿七福神 福禄寿を祀っています。 極彩色の美しい拝殿の石段の横に、「四十三貫目・七十貫目・三十八貫目 三個の力石」が置かれていました。 境内の「狛犬」は、足立区内で一番大きく浅草神社の狛犬と兄弟であるともいわれています。 社務所前の植え込みの中に、表情の怖い「狛犬」が潜んでいました。    明神型鳥居と寺院名碑 拝殿 拝殿前の石灯篭    三個の力石 福禄寿像 石灯篭   和風獅子型狛犬 東側の明神型鳥居 文政十三年(1830) 造立   社務所前の狛犬 同 拡大画像 更に千住大橋駅に歩を進めると、マンションの角に小さな「稲荷社」がありました。   稲荷社 お狐様 日光街道の正面に、千住大橋駅の標識が見えます。 川原町稲荷神社から200m、11時20分に駅舎に着きました。   日光街道を跨ぐ京成本線 千住大橋駅 これで、2006年10月からの積み残しであった「千住七福神巡り」を完了しました。 千住七福神は、2007年までは神社3箇所・寺院4箇所で行われていましたが、2008年よりすべて神社となったよう です。 |