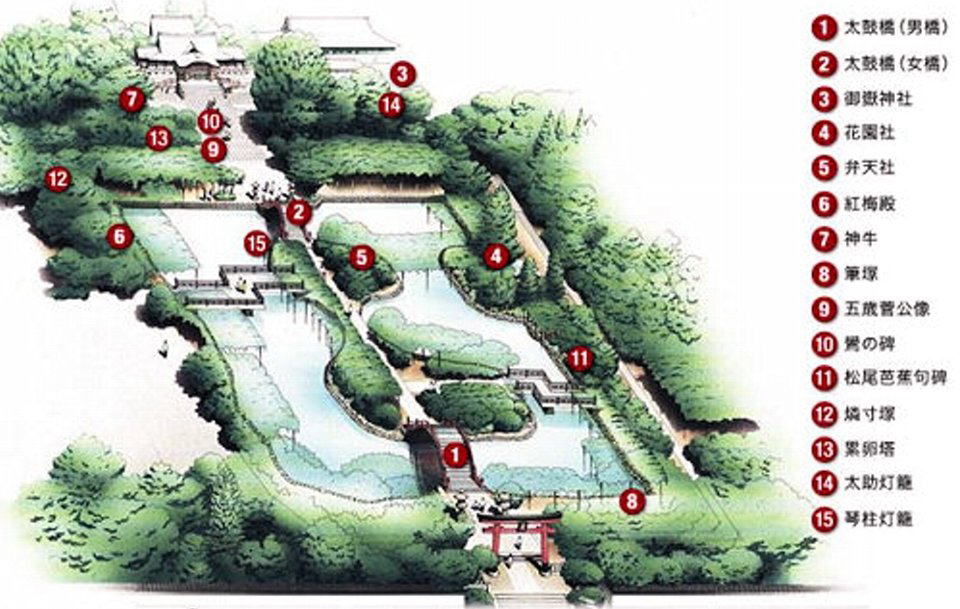| 亀戸七福神巡り |
|
江東区の亀戸七福神は、四方を 浅草通り(都道453号線)・丸八通り(都道476号線)・蔵前橋通り(都道315号線)・横十間川に囲まれたエリア内に点在する、4つの寺院と2つの神社(亀戸香取神社は、2神を祀る)からなっています。 併せて、エリア内の東京十社「亀戸天神社」もルートに入れました。 10時総武線亀戸駅北口をスタートです。 駅前を南北に走る明治通り(都道306号線)を北へ進みます。 亀戸四丁目交差点を右折し、蔵前橋通り(都道315号線)に沿った脇道を進みます。    亀戸駅北口 総武線の高架 明治通り   亀戸四丁目交差点 蔵前橋通りの脇道 亀戸駅から550m、赤門が印象的な「鏡智山寶蔵院浄心寺」があります。 境内には、左に「六地蔵像」右に江東区登録文化財の「四体の地蔵像」が祀られています。 墓地の入口に、関東大震災時に生じた「亀戸事件犠牲者之碑」が祀られていました。    山門 境内右側 六地蔵像 境内右側 石仏    同 地蔵菩薩像・子安地蔵像 同 水子地蔵像 同 地蔵菩薩像   本堂 亀戸事件犠牲者之碑 脇道から蔵前橋通りの信号に出ると、正面に神社が見えます。   脇道を北に行くと信号 交差点の先の角に神社 浄心寺から100m、蔵前橋通りに面して「東林山華蔵院寶蓮寺」があります。 江東区登録文化財を含む三基の「宝篋印塔」がありました。
|